3.慶應義塾大学総合政策学部に次女が合格(SMさん、東京都)
東京都立の中等教育学校に通う次女は、4年生(高校1年に相当)のころから「SFC(慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス)にAO入試で入学する」と決めていました。初めは「塾には通わない」と言っていたのですが、5年生の春に大学進学イベントでクロイワ先生の講演を聴き、相談コーナーでお話してから、「指導を受けてもいい?」とお願いしてきました。1回のみ対面指導(総合・推薦基礎コース)を受けさせたところ「絶対に合格するから。ここ以外は塾とか行かないから」という条件を自ら提示してきたため、追加で5回コースに申し込ませていただきました。
・朝な夕なにヘルメスゼミ®にLINEで質問攻勢の日々でした
おっとりした長女と違いって「やる」と決めたらとことんやるタイプの次女は、申し込んだ途端にメールやLINEで朝な夕なにクロイワ先生に質問をしていました。SFCで学ぶべきこと(近未来)と大学卒業後に進むべき道(遠未来)がなかなか絞り込めなかったためです。クロイワ先生は出張先からも丁寧に質問に答えてくださり、娘も徐々に自分のやりたいことが観えてきたようでした。
決して「これを書け」と押し付けるのではなく、娘との対話を通じて将来設計のお手伝いをしてくださったことが、書類審査の後の面接でも堂々とプレゼンでき、第一志望に合格できた要因だと思います。そして、そこがヘルメスゼミ®を受講させて最もよかった点です。
・柔軟性・寛容性が身につき自信を持って発言できるようになりました
学校や以前通っていた塾では、答えが一つに決まることばかり教えます。「これは正解。あれは不正解」と決めつける教育を受けていたためか、次女には行動力はあるのですが「正解への近道」を焦るばかりにせっかちで排他的なところがありました。それゆえ、初回の面談のとき「どんなことを書けば受かりますか」とクロイワ先生に質問したとき、先生から「それをこれから創っていくんだよ」と返されたため、キョトンとしていました。
クロイワ先生は「えぇ、創っちゃっていいんですか?」と間抜けな反応をした娘をこう諭しました。「志望理由書は過去のことではなく未来のことを中心に書くものです。未来はボーっと待っていれば来るものじゃない。前にある無数の道から一つずつ選択し、デザインするものです。だから、どのようにでも創れる。私が高校生のころはAO入試なんてなかった。だから、私が高校生のときに『将来はAO入試の先生になる』なんていう夢は描けなかった。でも、今は実際にこういうふうにAO入試の先生をやっているよね。それは自分でそう決めたから。自分の持っている知識、技術、価値観がそっちに向いているって確信を持てたからヘルメスゼミ®なんて勝手に創っちゃって、AO入試指導をしちゃっている。SFCだって私が高校生のころは慶應の中になかったんだよ。お亡くなりになったけど加藤寛先生という経済学部にいた先生が『未来からの留学生を受け容れるために自然豊かな神奈川県藤沢市に新しいキャンパスを創ろう』って言い出しっぺになって創ったんだ。だから、あなたの未来もあなたがこれから責任を持って創らなきゃいけないんだ」。
それからというもの、以前は「あの子はレベルが低いからせいぜいあの大学」などと言ってはばからなかった娘も、「○○ちゃんは彼女なりの想いで保育士になろうと女子大を目指しているんだ。そういうのもありだし、私がSFCを目指すのもありだよね」などと柔軟になり、多様性に対して寛容になっていきました。そして、それまでは反対意見を出されると、やり込めようとするか、逆に議論に負けて凹むか、いずれかだったのですが、「お姉ちゃんはお姉ちゃん。私は私」と自信を持ってものを言えるようになりました。母親としては、むしろ将来的なことを考えると、こうした変化の方が嬉しかったです。
・夢は政治家か官僚、漠然とですが将来設計もできていきました
志望理由書をまとめていく中で、今の日本の投票率の低さに疑問を持ったり、政治に参加しないことが自分自身の首を絞めることになることにも気づいたり、精神的な部分だけでなく、次女は教養力もかなり高めていきました。そして、自然に政治学や民主主義に興味を持ち、「環境情報よりも総合政策だな」と学部も自分で腹落ちして決めました。そして、「将来は政治参加を促して日本を民主主義国家としてもっと成熟させよう。そのために政治家か官僚を目指そう」という遠未来も描けてきました。
そして、その背景にある動機として自らが携わってきた生徒会活動、親せきの都議会議員の選挙応援活動、選挙権の年齢引き下げなど、自らが体験してきたことを交えて書類を完成させ、合格に至りました。クロイワ先生が仰った「未来は自分で創るもの」という言葉は私の頭にも残り続けています。そう、第一志望の大学に合格したのも、娘の選択の結果。もしかしたら、これから私たち保護者が予想もしない選択をする可能性もある。そのときはそのときで「この子の選択」として甘んじて受け容れよう。気づいたら私自身も柔軟かつ寛容な親になっていました。

 HERMES
ヘルメス株式会社
ヘルメスゼミ
HERMES
ヘルメス株式会社
ヘルメスゼミ


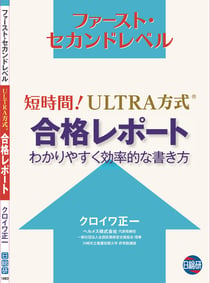
コメントをお書きください